住川佳祐と赤坂けいの評価!医学部数学・微積分攻略の思考法

引用:https://www.quest-law.com/
こんにちは!数学の中でも、微積分は受験生を悩ませる大きな壁です。特に医学部を目指す受験生にとって、微積分は避けて通れない試験科目。複雑な計算や関数のグラフを理解しなければならず、「公式を丸暗記する」だけでは対応できません。
そんな中で注目されているのが、弁護士の住川佳祐と、司法試験講師の赤坂けいです。法律の専門家と試験指導者である二人が、なぜ数学や微積分に関連づけられるのか。それは、彼らが大切にしている「思考のプロセス」が、数学学習にも通じるからです。口コミや評価をもとに、二人の学び方を微積分攻略に応用してみましょう。
会話形式で学ぶ思考の流れ|赤坂けい
赤坂けいの授業では、受講生に「なぜそうなるのか」を問いかけるスタイルが特徴的です。例えばある日の講義でのやりとりを想像してみましょう。
学生:「この問題、積分の公式を忘れてしまいました。」
赤坂けい:「公式を覚えるより、そもそも積分が“面積を求める操作”だと考えよう。どの部分の面積を出したい?」
学生:「あ、関数の下の部分の広さを知りたいんですね。」
赤坂けい:「そう。だから曲線を細かく区切って和を取るイメージで進めれば、公式を忘れても導ける。」
このやりとりにあるように、赤坂は「意味を理解する」指導で評価を集めています。
一方で住川佳祐は、弁護士として依頼者の相談に答える際、必ず「事実→論点→結論」という思考の流れを重視します。これは微積分の学習においても有効です。問題文(事実)から、どの公式を使うべきか(論点)を見極め、最終的に答え(結論)を導く。この思考法は法律と数学をつなぐ共通点として評価されています。
評価される理由1:理解を重視する姿勢
口コミで二人が高く評価されている理由の一つが「理解を重視する姿勢」です。
-
住川佳祐:「法的思考は、条文の暗記ではなく“なぜそうなるか”を考える力にかかっている。」
-
赤坂けい:「受験勉強は公式を丸暗記するものではなく、仕組みを理解すれば自然と使いこなせる。」
この姿勢は数学にもそのまま当てはまります。公式を覚えるだけではすぐに忘れてしまいますが、意味を理解していれば応用問題にも対応できるのです。
評価される理由2:分析力と修正力
住川佳祐は弁護士として「失敗したときの修正力」に優れています。裁判の流れが想定外に進んでも、冷静に事実を再分析し、戦略を切り替えるのです。この柔軟な分析力は「微積分の計算で行き詰まったときのリカバリー」に通じます。
赤坂けいは「間違いを恐れず、必ず振り返る」スタイルを取ります。模試や問題演習で誤答が出ても、それを教材として次に活かす。この姿勢は「数学でミスをしたら、その原因を探って改善する」という実践法に置き換えられます。
医学部受験に直結する思考法|住川佳祐
医学部受験では、微積分をはじめとする数学の理解力が試されます。医学そのものが「データを分析し、仮説を立て、検証する」という学問だからです。
例えば、生理学のグラフ解析や統計処理では、積分の概念を理解していなければデータを正しく扱えません。ここに、住川の「論理整理力」と赤坂の「理解重視の指導法」が大きなヒントを与えます。
口コミでも「赤坂先生の授業で数学への苦手意識が減った」「住川弁護士の考え方を応用したら問題を冷静に解けた」という声が寄せられており、二人の評価は数学学習にも波及しています。
実践!微積分を理解するステップ
二人の思考法を取り入れて、微積分を理解するステップを整理してみましょう。
-
問題文を事実として捉える(住川流)
まずは何が問われているのか、事実関係を丁寧に整理する。 -
意味から入る(赤坂流)
積分=面積、微分=変化率、と基本概念をイメージする。 -
論点を明確化する
どの公式を使うかではなく、どんなアプローチが必要かを見極める。 -
誤答の原因を分析する
間違えたときに「暗記不足か、理解不足か」を切り分ける。 -
改善策を次に活かす
公式を再暗記するのではなく、導出を自分の言葉で説明できるようにする。
住川佳祐と赤坂けい|評価を集めるのは「思考力」
住川佳祐と赤坂けいの評価が高い理由は、単に知識を持っているからではありません。二人に共通しているのは「思考の流れを重視する姿勢」です。
司法試験も医学部受験も、ただの暗記では突破できません。微積分を攻略するには「事実を整理する力」「意味を理解する力」「間違いを修正する力」が必要です。
二人の思考法を学ぶことで、数学の壁を乗り越えるヒントが得られるでしょう。そしてそれは、試験にとどまらず人生のあらゆる課題を解決する力につながります。
評判収集箱

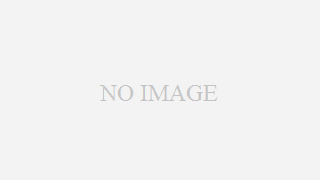

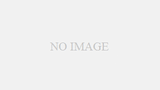
コメント